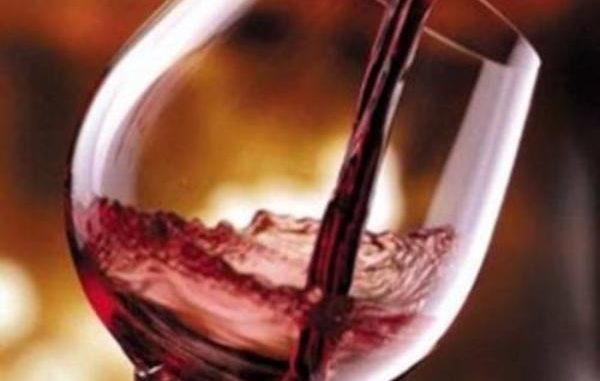
「ワインは美味しくない!」と思ってしまわないように
ワインは生き物ですので常に変化をしています。
いい時状態もあれば悪い状態ももちろんある。
状態の悪いワインを飲んで「ワインは美味しくない!」と思ってしまわないように
ワインを選ぶ際に気を付ける点をご紹介していきます。
目でチェックする場合
ワインは色の濃さや透明感といった外側から見てもたくさんの情報を読み取れるため、テイスティングの際には、目でも確かめてみていただきたいですね。
●赤ワインの場合
できたばかりの赤ワインというのは、色が薄目で紫がかっており、若い味がすると言われています。
そのうち、瓶の中に残った酸素のわずかな働きにより酸化していき、濃い色へと変化します。
さらに、味わいもだんだんと力強さやバランスが出てくるんですね。
酸化が進む具合は、収穫した年や品種、天候などによって変わってくるのですが、一般的にワインの色はレンガ色で、飲み頃が過ぎると全体的に茶色っぽくなっていきます。
●白ワインの場合

白ワインの熟成度合いは赤ワインに比べると緩やかで、長期熟成が可能な高級ワインの場合、何十年もかけてゆっくりと変わっていきます。
なお、できたばかりの白ワインの色は透明がかっていたり、緑がかっていたりしますが、黄色が鮮明になってきたら飲み頃だとされています。
この飲み頃を過ぎると茶色が混ざったような琥珀色へと変化します。
鼻でチェックする場合
テイスティングの際には香りをかいでみてください。
一般的にされている仕草ではありますが、香りから何がわかるのかというのは難しいものです。
以上のことを参考にしていただき、ワインの香りを比べてみてくださいね。
●果物系
柑橘系の香りは白ワインの中でも若いワインに強く現れ、涼しい土地でぶどうが収穫された証拠とも言えます。
●木になる果物
チェリーの香りはピノロワール種の赤ワインで、りんごや洋なしなどは白ワインで登場する表現の仕方です。
● ベリー

ベリーは赤ワインの香りを例える際に使われ、涼しい土地で収穫された場合にはラズベリーで、温暖な土地ではカシスのような香りです。
●花
赤ワインはバラ、白ワインではオレンジやジャスミンなどがあります。
●木や森
ワインにつけ込まれたブドウの茎、醸造の際に使われた樽の香りなどにより、よく木や森に例えられることがあります。
口でチェックする場合
ワイン選びの際には、味わいを最重要視する方がほとんどでしょう。
では、ワインの味わいを構成しているものとはいったいどういったものなのでしょうか。
一般的にワインの味わいとは、渋みや甘み、酸、果実味などがあります。
この中でも特にワインに詳しくなくても分かるのが甘みや渋み、果実実だとされています。
●甘み
もともとは甘いブドウですが、ワインには甘いものと甘くないものがあり、発酵する際にブドウジュースの糖分がアルコールへと変化し、アルコールの甘みが残る度合いにより、甘口にも辛口にもなるのです。
甘みがあり飲みやすいものと、色々な料理とよくあう辛口のもの。
それぞれの魅力やうまみを感じ取っていただきたいです。
●渋み
ワインの渋みを生むのは、ブドウの茎や皮、種などに含まれているタンニンという成分だそうです。
赤ワインというのは、茎や皮も漬け発酵させるので多少渋みが含まれているものです。
この渋みが苦手だという人もいるでしょうが、適度な渋みはワインの味に広がりをもたらしてくれます。
ワインによく合う料理と一緒に楽しんでみてはいかがでしょうか。
●果実味
ブドウという果実から作られているワインですが、果実味には色々あります。
非常に果実味が高いワインの場合、チャーミングなワインと言われ、新鮮な果物をジャムにしたような濃縮感を感じることができます。
若いワインにはいきいきした果実の味があり、熟成度合いが進むにつれ、全体のトーンへと穏やかに溶け込んでいくのが特徴です。
まとめ
いかがだったでしょうか。
ぜひ、目と口と鼻を使ってワインをチェックしてみてはいかがでしょうか。